 |
|
 |
 |
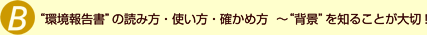 |
 |
|
| 2)環境報告書の構成要素に着目 |
|
さまざまな企業が、それぞれに環境保全のための活動を報告する環境報告書。業種もちがえば規模もちがう……とはいうものの、共通の“構成要素”は存在します。これを、あらかじめ知っておくと読みやすさもアップするはず、あるいは、共通部分を読みくらべることで新たな興味がわくケースもある、というわけで、おもなものをピックアップしてみました。
共通といっても、現段階では、企業によって用いる用語や表現の方法がまちまちという場合もあります。でも、ほぼ環境報告書に“なくてはならない”といえそうな要素です。 |
|
| ◎ |
報告書の“前提”を提示している部分 |
|
|
大切なのは、報告書の対象となっている期間と範囲を明らかにすること。とくに、多くの子会社・関連企業をふくむグループ企業などでは、対象となる組織についてはっきりさせなくてはいけません。事業概要では、所在地、創立・創業時期、資本金、従業員数とならんで、生産実績や売上高、経常利益などを掲載することも一般的になっています。このほか、報告書の作成部署、読者からの問い合わせ先もこの部分に書かれることが多いようです。
|
|
| ◎ |
理念、方針をあきらかにする部分 |
|
|
[経営トップのコミットメント]
環境保全活動が、あくまでも自主的な活動である以上、誰が最終的な責任を負うかということを明確に記す必要があります。そこで、社長または会長が社会に対して、誓約(コミットメント)を行う意味が出てきます。明記すべきは、環境保全活動を、事業活動のなかでどのように位置づけているかということ、そして環境情報開示に関する方針について。これを、社会に対して誓約するわけです。
[全社的な宣言]
その事業者の、環境に対する取り組みの姿勢をあらわすところ。環境に関して、事業の内容と関連した活動をどのように行うのか、環境保全について今後の方向性や重点項目について述べます。消費者、投資家、地域住民、従業員など、あらゆる利害関係者にとってわかりやすく、明快であることが大切です。
|
|
 |
|
| ◎ |
行動の実績をレポートする部分 |
|
|
[環境負荷の全体像]
事業活動によって生じる環境負荷の種類、質量などについて、公表します。商品やサービスのライフサイクル全体を通して、原料調達から製造、輸送、使用、廃棄・リサイクル時までを、インプットとアウトプットで表し、フロー図などで説明しているケースが一般的です。
[環境負荷を低減する取り組み]
環境負荷を低減するための対策や成果を報告する部分。各社で行われているのは、省エネルギー、原材料や資材、事務用品などに環境対応商品を選ぶ“グリーン調達”、廃棄物の削減およびリサイクルの推進、環境配慮型商品やサービスの開発などの対策です。これらについて、自ら定めた目標値に対する達成状況と、今後の目標を発表しています。
[環境会計]
環境保全活動にかかったコストと効果をあきらかにするためのもの。効果について、金額換算して表示するか、物量単位で表示するかも、企業によって異なるなど、“会計”とはいっても、業種や規模、環境への取り組み方、データの集計方法などによって、さまざまな表現方法があります。
[環境マネジメントシステム]
環境保全活動を行うためのツールのひとつ。さまざまな体系がありますが、国際規格の“ISO14001”を導入し、認証取得をめざすケースが増えています。これは、“PDCAサイクル=Plan(方針・計画)→ Do(実施) → Check(点検) → Action(是正・見直し)”のプロセスを繰り返しつつ、継続的なレベルアップをはかろうという取り組みです。
[環境配慮型商品とサービスの開発]
製品のライフサイクルでは、製造時だけでなく、資材の調達・使用・廃棄時の環境負荷も見逃せません。そこで、製品の原材料から最終段階までトータルに考える、環境負荷対策が必要になります。省資源、環境に配慮した資材の使用、消費電力の低減化、小型・軽量化、リサイクル性の向上などのために、環境に配慮した商品やサービスの開発についての現状報告をします。
[社会貢献活動]
各組織が行う、環境に関連した非営利活動を記載するところ。自然保護活動や地域との共生をめざしたイベント、フェアなど、環境啓蒙活動ともいえる要素をもっています。
|
|