|
|
■ |
もっと速く走りたい人の
トレーニング |
|
最後に、“ゆっくり走る”の次のトレーニングについて、すこしだけ紹介します。スピードを向上させるためのトレーニング、あるいはスピードをより長く持続するためのトレーニングについて知っておくことで、みなさんに、もっともっと走ることに興味をもってもらえればと思っています。 |
|
|
 |
|
|
■ |
インターバル・トレーニング |
|
|
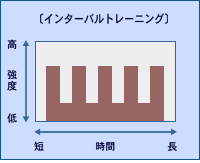 |
| インターバル・トレーニングは、運動強度の高い急走期と、低い緩走期を繰りかえすのが特徴。その組みあわせにより、いろいろなパターンのインターバル・トレーニングが存在している(赤い部分は、活動期をしめす)。 |
|
『インターバル・トレーニング』とは、スピードを持続させる能力(スピード持久力)を高めるためのトレーニングとしておこなわれています。このインターバル・トレーニングを有名にした人物は、20世紀の中盤に活躍し、“人間機関車”という異名をもつエミール・ザトペック選手(旧チェコスロバキア)なのです。
そのザトペック選手が、1952年のヘルシンキオリンピックで、“5,000m”“10,000m”“マラソン”の3種目で優勝したことによって、インターバル・トレーニングは世界中に広まっていったのです。彼が実施していた方法は、400mを60秒台で走る急走期と、200mをはやいペースでジョギングする緩走期を何十回も繰りかえしたものでした。
現在では、ザトペック選手のように何十回も繰りかえす方法はおこわれませんが、急走期と緩走期の距離やスピードの組みあわせによって、さまざまなインターバル・トレーニングが実施されています。 |
|
|
 |
|
|
■ |
そのほかのトレーニング方法 |
|
そのほかにも、さまざまなトレーニング方法があります。たとえば、スピード養成のためのトレーニングとして、全力走と完全休息を繰りかえす『レペティション・トレーニング』、すこしずつ走るペースを上げていく『ビルドアップトレーニング』、ベストタイムの7〜8割程度のペースで走る『ペース走』、レースの目標タイムで走る『レースペース走』、起伏にとんだコースを走る『アップダウン走』などが、代表的なトレーニング方法と考えられます。
また、乳酸性機構が働きはじめるペースで走るトレーニングもあります。疲労物質である乳酸が、筋肉内で生産されはじめる運動強度を“乳酸性閾値(Lactate threshold、LT)”といいます。このLTかLTをやや超える運動強度に相当するペースで走るトレーニングを、『LTトレーニング』というのです。このトレーニングをおこなうと、効果的にLTが上昇していきます。LTが上昇するということは、有酸素性機構で走ることのできるペースが上昇することになりますから、より速いスピードで走ることができるようになるのです。
これらのトレーニングについては、もうちょっとみなさんの走りこみが進んだときに、もう一度、くわしく取りあげてみたいと思っていますので、まずは、ゆっくりペースで長く走ることを目標に、これからもランちゃんといっしょに走っていきましょう! |
|
|
 |
|
 |
|
| (文:水村 信二 〜 プロファイルはこちらへ) |
|



