|
|
■ |
“クレアチン”ってなに? |
|
“クレアチン”って聞いたことありませんか? もし、あなたが、陸上競技、野球、サッカー、テニス、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、柔道、空手、あるいはアイスホッケーなどのパワー系の競技選手なら、きっと聞いたことがあるでしょう。
1992年のバルセロナ・オリンピックで、イギリスの陸上短距離のエース、リンフォード・クリスティーが“クレアチン”を摂取して大会にのぞんだ結果、好成績を残したことがあります。彼は、あのカール・ルイスを破り、100mで金メダルを獲得したのでした。それ以来、“クレアチン”摂取は、競技スポーツの世界にひろまっていったようです。1996年アトランタ・オリンピック、2000年シドニー・オリンピックで活躍した200m、400mのマイケル・ジョンソン選手も、“クレアチン”を摂取していると伝えられています。
なぜ、リンフォード・クリスティーは、“クレアチン”を摂取したのでしょうか? 走るために欠かせない筋肉の働きを知ることによって、そんな疑問を解くヒントがみえてきます。そこで今回は、筋肉の内部で起こっているさまざまな反応と、ランニングとの関係について紹介します。 |
|
|
 |
|
|
■ |
筋肉はエンジンだ! |
|
自動車や飛行機は、エンジンの原動力で動きます。動く機械はかならず原動力を作りだす原動機をもっています。電車やケーブルカーの場合、原動機はモーターとなります。では、人間の場合、原動機に相当するのはなんでしょう? 答えは“筋肉”です。筋肉が動くことによって、走る、跳ぶ、蹴る、投げる、打つなどのスポーツの基本動作ばかりでなく、話す、食べる、立つ、文字を書くなどの、日常生活におけるあらゆる動作をすることができるのです。
そうです、筋肉はエンジンなのです! 私たちは、走るときに筋肉の内部で起こっていることを意識する必要はありません。しかし、走るときには、その内部ではじつにダイナミックな反応がつぎつぎと起こっているのです。そして、筋肉の内部でどんな反応が起こっているかを学ぶことは、それを応用することによって、“より速く”“より効果的に”“より長時間”走るための手助けとなるのです。 |
|
|
 |
|
|
■ |
筋肉のガソリンはATP |
|
|
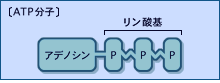 |
| ATPは、アデノシンとよばれる大きな分子が1つと、小さなリン酸の分子が3つつながってできている。これが筋肉を動かすエネルギー源なのだ! |
|
ところで、自動車の場合、エンジンを動かすエネルギー源はガソリンです。ガソリンの燃焼による爆発で、ピストンが動くわけです。おなじように、人間のエンジン、筋肉のなかにも、自動車のガソリンにあたるものがあるのです。それが、“ATP(アデノシン3リン酸)”と呼ばれ、筋肉にごく少量たくわえられている、高エネルギー化合物なのです。 |
|
|
|
|
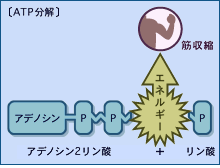 |
| ATPからリン酸が1つはずれ、ADPになったとき、筋肉が収縮するエネルギーが発生する。これにより、私たちはスポーツだけでなく、日常生活の動作もおこなうことができる。 |
|
よくみてみると、ATPはアデノシンにリン酸が3つ結合している物質ということがわかります。そのATPからリン酸が1つはずれるときには大きなエネルギーが放出され、ATPは、ADP(アデノシン2リン酸)とリン酸という物質に分解されるのです。つまり、ガソリンが爆発してピストンを動かし、自動車を走らせるのと同様に、ATPからリン酸が1つはずれるときに放出されるエネルギーによって、筋肉が収縮する。それによって、人間は走ることが可能になるのです。 |
|
 |
|
 |
|
| (文:水村 信二) |
|



