
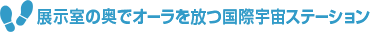 「かぐや」に別れを告げて先へ進むと、H-IIロケットに使われた本物のLE-7エンジンや、ロシアの宇宙船ソユーズの帰還カプセル(実物大模型)、あの天気予報でおなじみの気象衛星「ひまわり」1号モデルなどが置かれていました。 現在運用中の「ひまわり」は6号にあたり、搭載したロケットを打ち上げるのは種子島宇宙センターですが、その後の追跡管制やデータ受信などは、すべてこの筑波宇宙センターで行われているそうです。 ひそかに驚いたのが、人工衛星ALOS(だいち)の試験機。金色に輝く断熱材が全面に貼られているのですが、これらの断熱材はボディにマジックテープでとめてあるだけでした。「宇宙空間は無風状態で、雨が降ることもありませんから、これくらいの強度でも問題ないのです」。なるほど。 そして、この建物の最も奥でぼくらを待っていたのが、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」でした。飛行士2名が実験を行うという船内実験室、宇宙空間で実験装置を作動させるための船外実験プラットフォーム、そうした実験装置を操るロボットアームなどの実物大模型が並んでいます。 「『きぼう』は宇宙における日本初の有人施設です。アメリカへ運ばれた後、スペースシャトルで3月から3回に分けて打ち上げられ、国際宇宙ステーションに取り付けられます」。 と、宍戸さんが解説してくれました。「きぼう」を宇宙へ運ぶシャトルには、先日無事に帰還した土井隆雄さんにつづいて、星出彰彦さん、若田光一さんが順に搭乗予定。アメリカやカナダ、ロシア、ESA(欧州宇宙機関)が参加する国際宇宙ステーションは、完成するとサッカー場ほどの大きさになるそうです。 「その中でも船外実験ができるのは日本実験棟だけなので、おそらく世界中の注目を浴びることになると思いますよ」。 それは、何億もの人々を救うことになる新薬かもしれません。かつてないほど環境にやさしい新素材かもしれません。高度400kmの軌道に浮かぶ、われらが日本実験棟から、人類の未来に役立つなにかが生まれるとしたら……そう考えただけで、わくわくしてしまいます。 |