
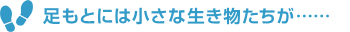 入り口からわずか数メートル歩いたところで、さっそく土田さんが立ち止まりました。土に転がっていた、くるんと巻かれた1cmほどの葉っぱを指さし、 「ほら、オトシブミの揺籃(ようらん)ですよ」。 「昆虫の名前です。餌になる葉っぱを巻いて中に巣を作り、卵を産みつけるんですが、その形状が、落とし文に似ていることから名づけられました。卵から孵(かえ)った幼虫は、中で葉を食べて成長し、サナギになるんですよ」。 なんと風流な名前、そして餌をセットにして卵を産むとは、なんという知恵でしょうか。名づけ親のコピーセンスと虫の母性愛に感動しつつ歩を進めると、せかせかと地面を這う昆虫を踏みそうになり、思わず足をよけます。 「あ、これ、センチゴガネです」土田さん、すかさずアンサー。おセンチなこがね虫かと思いきや、センチとは雪隠(せっちん)=トイレから。つまり、獣糞を好む黄金虫なのでした。まさに、蓼食う虫も好きずき、という諺通りだなあ、と呟きつつ、昆虫の食生活の多様性に思いを巡らせていると、今度は木陰にひっそり咲く、スズランに似た、まるで妖精の化身のような野草にうっとり、もう目は釘づけです。 「銀らんです。これに姿形が似ている金らんもあるんですよ」と土田さん。可憐な野草にため息をつきながら、夏にはいちばん人気という「カブトムシの丘」を過ぎ、ミズスマシの沢に到着。ここからカエル池に至る道は、色とりどりの野草が風にゆらゆらそよぎ、まるでモネの絵のような詩情あふれる風景が続きます。 「野草の花の色って、白が圧倒的に多いんですよ。なぜなら、花粉を運んでくれる昆虫が識別しやすい色だからなんです」。 なるほど。単にきれいね〜ですまされない、植物たちの生存へのあくなき戦いをかいま見て、身が引き締まる思いです。 |