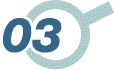|
|
|
燃料電池とマイクロガスタービン
|
NN:具体的にはどのような技術を開発していらっしゃるのでしょうか?
TG:有効にエネルギーを使うための技術としては、“コージェネレーション”があります。コージェネレーションとは、地域や、ビル、家庭など電気を使う場所で発電し、発電の際に発生する熱を回収して、暖房、給湯、冷房に利用する技術です。
*[コージェネレーション]についてのくわしい説明は、
以下のページを参考にしてください。
http://www.tokyo-gas.co.jp/env/earth/spread.html
電力やエネルギーを使う場所の近くでつくり、供給することを、発電所など一極“集中型”に対して、“分散型”といいます。分散型は、発電効率では高効率な集中型に劣りますが、送電の際のロスはなくなりますし、発電時に発生する熱も有効利用できます。熱の有効利用まで入れると、分散型は、集中型に対し20%程度、省エネ効果があるといわれています。
NN:コージェネレーションシステムは、実際、どれくらい使われているのでしょうか?
TG:コージェネレーションシステムは、いままではジェット機に積んでいるようなガスタービンとか、ガスエンジンとかを使って、大きなビルなどに利用されてきました。今日お越しいただいている、この本社ビルもコージェネを使っています。
しかし、レストランや家庭など小さなスケールでコージェネを使うためには、機器を小型化することが必要不可欠です。そこで最近力を入れているのが、“固体高分子型燃料電池(PEFC)コージェネレーション”と“マイクロガスタービン・コージェネレーション”です。
[燃料電池]とは、水素と酸素を電気化学反応させて、電気を発生させる発電装置です。現在、車でも実用化が検討されているのが、電解質に高分子膜を採用した固体高分子型燃料電池です。固体高分子型燃料電池は、常温〜90℃という低温で動作するのが特徴で、従来の燃料電池よりも省スペースで、家庭でも利用できる大きさにすることができます。
ガス管のネットワークが各家庭に行き届いていますので、各家庭に供給されたガスをそこで改質し、水素を発生させて燃料電池で発電をし、かつ熱もエネルギーとして回収しようというのが、この固体高分子型コージェネレーションです。東京ガスでは、ガスを改質して水素を取り出す技術の開発をしています。
そしてもう1つが、ファミリーレストラン、コンビニなどで使えるコージェネ、すなわちマイクロガスタービン・コージェネレーションです。タービンそのものはメーカーの技術を活用していますが、そこから熱をどう取り出していくかを、東京ガスは主に開発しています。
NN:これらの技術は、もうすぐ私たちの家庭など、身近なところにまでやってくるのでしょうか?
TG:燃料電池は、2004年の実用化を目標としています。一般家庭に普及させるには価格を下げたり、長時間運用に耐えられるように改良を加えていかなくてはなりません。マイクロガスタービンは、アメリカなどでは非常用などに使われていますが、いかに省エネルギーシステムのパッケージとして提案できるかが、実用化の鍵になると思われます。
|
|
■家庭用燃料電池コージェネの構成と導入イメージ
|
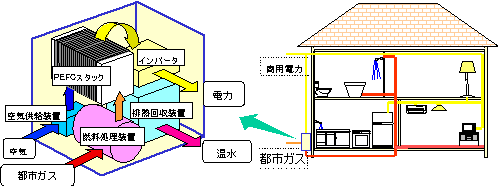
|
|
[出典]東京ガス
|
|