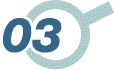|
|
|
“環境適合性”から、ほんとうに必要なサービスを見つけだす
|
NN:そんな宝酒造といえども、ワンウェイ容器も使っていらっしゃいますが、こちらの対策はいかがでしょうか?
TS:いままでは、お客さまへアピールするために、多くの資源、エネルギーを使い、過剰なサービスを付加することにより他社と競争するというケースがよくありました。しかし、ほんとうにそのサービスがお客さまに必要なのか、それを見直すことからはじめました。
たとえば、焼酎のペットボトルは、以前、取っ手がついていました。その取っ手がリサイクルの障害になっていたのですが、取っ手の代わりに、ペットボトルに持ちやすいように“くぼみ”をつけてみました。こうすることによって、リサイクルの効率が上がり、同時にコストの削減にもつながり、売り上げも上がりました。
いままでは商品の仕様を決める際にも、消費者便宜性、品質保持性、デザイン優位性などが、環境問題よりも優先されていました。そうすると、どうしても過剰なモノをつくってしまう。それを“環境適合性”という軸から適切なところを見直すと、過剰なサービスがなくなって、コストも下がり、環境にもよくなります。
NN:一見、環境と経済は相反するように思えますが……。
TS:究極の局面ではそのとおりです。しかし、経済のなかにまだまだムダなモノがあるんですね。このムダがある限り、経済と環境は両立します。つまり、経済性を追求してコストを削減すれば、環境面でも改善されるという関係です。電力とかエネルギー資源が、まさにそのよい例です。ムダをコストの面からだけでなく、環境の面から見直していきましょうということが、われわれのリサイクル活動です。
NN:そうですね。消費者もそういう観点から、商品を見直さなくては。それでは、ガラスびんについてはどのような施策があるのでしょう? お酒の一升びんは、リターナブルですが、それ以外のガラスびん、とくに茶色と透明以外のカラーびんを私たちは自治体の回収に出します。しかしリサイクルするのがむずかしいと聞いていますが……。
TS:2000年7月から、“エコロジーボトル”を使って清酒を販売しています。エコロジーボトルというのは、90%までいろいろな色のボトルから出たカレットを使い、あとの10%は、当社が望む色を出すための原料を入れて、最終的に一定の色を出す技術です。
NN:(しつこいと言われることを覚悟して!)それでは、カンについてはいかがでしょうか?
TS:(待ってました?!)カンはアルミカン79%、スチールカン83%と、非常に回収・リサイクル率がよいのです。そこですべきことは散乱防止です。今年で10年目になりますが、湘南海岸で市民の方々に参加してもらい、浜辺で空きカンをひろう“クリーンCAN ウォーキング”という活動をしています。これは、緑字決算の一方の柱である社会貢献活動の環境啓発・教育の一環として行っています。毎年1,000人以上の市民の方々に参加していただいています。じつは、今年も今週の土曜日にあるんですよ。
NN:それは、ぜひ取材させていただきたいですね。
TS:ええ、ぜひ!
恐れ入りました! 自社の責任を明確にとらえ、世の中にとって正しいと思われることをこれほど思い切って実行している企業があるでしょうか。その姿勢は、宝酒造を一挙に環境対策の先進企業に押し上げた緑字報告書にもよく表れています。NNの読者のみなさん、酒屋さんに行ったら、宝酒造の努力のたまものを再確認してください。そして、その努力に応えられる消費者になろうではありませんか!
|

ペットボトルには、リサイクルしやすい工夫を
|

びん入りの焼酎に関しては、リターナブルびんを増やす
|

回収されたカラーボトルをリサイクルし、清酒の容器に
|
|