
|
経済的に成り立つリサイクルビジネスとは? |
| A. 廃棄物に原料としての高い価値がある場合 |
|
バージン材からその素材を製造するより、廃棄物からリサイクルしたほうが安い場合は、当然ながら、ビジネスが成立します。容器包装リサイクル法の対象にはなっているものの、回収された廃棄物自体に大きな経済価値がある場合は、特定事業者から再商品化のための委託料を徴収する必要がありません。特定事業者も、リサイクルの義務も負いません。
◎アルミカンとスチールカン 原料のボーキサイトからアルミニウムの地金を作る際には、多大なエネルギーを必要とします。しかしアルミカンからリサイクルする場合は、そのたった3%しか必要となりません。 スチールカンもリサイクルすれば、原料の鉄鉱石からからスチールを製造する場合の37%のエネルギーですみます。ですから、アルミカンとスチールカンは、製造業者にすれば“競ってでも手に入れたい”安い原料ということになります。 ◎紙パックと段ボール 牛乳やジュースの1リットルパックに使われる 紙パックは、上質の天然パルプ100%でできています。この紙パック30枚からトイレットペーパー5個が再生されます。段ボールは、新しい段ボールに再生することができます。こちらも、自治体が回収した時点で有価で売却することができますから、経済的に成立しているということになり、特定事業者に再商品化の義務はありません。 こうした例のように、廃棄物にじゅうぶん資源としての価値があり、法で規制しなくても循環していく素材については、回収率を上げることが課題です。 アルミカンは78.5%(1999年)、スチールカンは82.9%(1999年)の回収率がすでにありますが、いまだに20%前後が廃棄されているということになります。もっと回収率を上げれば、それだけ安いコストで、貴重な天然資源を有効に活用することができるわけです。紙パックの回収率はまだ23%です。紙パックには上質の天然パルプが使われていますから、回収がいま以上に進めば、トイレットペーパーのみならず、コピー紙にも再生することが可能です。 |
| B. 容器包装リサイクル法の枠内において、経済的に成り立つ場合 |
|
自治体が回収した時点で、そのままでは有価売却できないもの……ガラスびん、ペットボトル、ペット以外のプラスチックの容器包装、紙パック・段ボール以外の紙容器……これらを生産・販売する特定事業者は、再商品化の義務を負います。独自の再商品化ルートがない場合は、日本容器包装リサイクル協会に処理委託費を払うことになります。
協会への委託費用は、ガラスびん4,000〜8,000円(1トンあたり)、ペットボトルで89,000円(同)、プラスチック容器で105,000円(同)となっており、協会では、今年度およそ280億円弱を回収することになるとしています。再商品化業者は、リサイクルが適切かどうかプラントのチェックを受け、入札でリサイクルを請けおいます。法規制によって処理費をまかなわなければならないということは、現状では再生品に市場競争力がないことを意味します。 ◎ガラスびん ガラスびんは、破砕してカレットにします。カレットからびんに再生しますが、再生びんの競争相手は、じつはガラスのバージン材ではなく、消費者にとって利便性の高いカンやペットボトルです。軽くて便利なカンやペットボトルにおされ、一時は年間約260万トン生産されていたガラスびんも、現在では160万トンにまで落ちこんでいます。 再生しても市場の需要が小さいので、カレットもだぶつき、価格は下降気味です。そのため、容器包装リサイクル法による委託料を受けないで、再商品化ビジネスを成り立たせることは、現状では困難です。びんのリサイクルのためには、新たな需要を開拓することが必要で、カレットから建材のグラスウール、ブロックなどに再生する技術が開発されています。 ビールびんや牛乳びんのようなリターナブルびんについては90%以上の回収率があるので、特定事業者は再商品化の義務を免除されます。 |
| ■リサイクル率等の推移 |
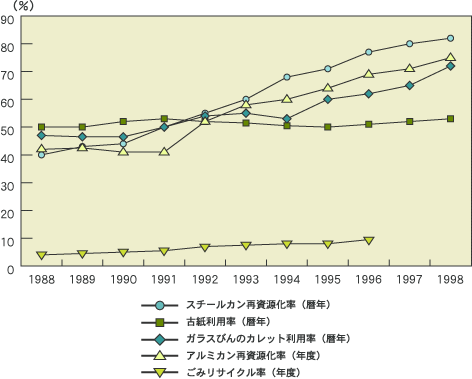
|
| [出典]平成12年版『環境白書』 |
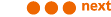 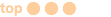 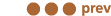
|