
|
環境効率のよい製品を選ぶ手段:ライフサイクル・アセスメント |
| たとえば、ビールをびんで提供し、びんを回収してリユースするのと、カンで提供しアルミをリサイクルするのでは、どちらが環境負荷が少ないのでしょうか。一見、リユースしたほうが環境によさそうです。ところが、ビンは重くかさばるので、運搬の際に燃料をたくさん消費し、CO2を排出する、という見方もあります。 このように、環境によい製品を作るにはどうしたらよいのかが、概念的にわかっても、実際どのように適用するのか、複数の選択肢が存在する、どちらを選ぶべきなのか迷う、といった場面が、現実には多いはずです。 このような場合、問題を概念的にとらえるのではなく、製品のライフサイクルすべての段階での環境負荷を定量的に表して、判断の基準にする手法が、[ライフサイクル・アセスメント:LCA]です。最近、ビジネスの場で、LCAについて語られることが多くなったと思います。ここで、少しその手法を検証してみたいと思います。 |
| ライフサイクル・アセスメントの手順 |
|
Step 1:目的・調査範囲の設定 LCAは、材料の投入から廃棄物/リサイクルまで広範囲をカバーしているので、なにが目的か、どの範囲を調査対象とするかを明確にすることが、調査の無駄をなくし、調査の有効性を高めます。複数の選択肢でも共通部分があるなら、共通部分を調査する必要はないでしょう。 Step 2:インベントリー分析 製品のライフサイクル全段階で、投入された原料、エネルギー、排出された物質をリストアップし、それぞれについてのデータをつくります。製品に使われる素材の種類が、多ければ多いほどその作業は膨大です。エネルギー消費に関して最も重要な二酸化炭素については、次の2種類の手法があります。 ◎積み上げ法:それぞれのインプット、アウトプットの構成要素についてデータを集め、集計する方法。直接的な積み上げ法のほうが正確な数値を得られますから 使っている素材の種類が少ない場合は、この方法のほうが信頼性はあると思われます。 ◎産業関連表を利用する:環境庁国立環境研究所の地球環境研究センターでは、産業関連表から、“二酸化炭素排出原単位”データベースを5年ごとに算出しています。これにより、自動車1台あたりの製造段階における二酸化炭素の放出量を間接的に求めることができます。使っている素材が多い製品の場合は、この手法のほうが簡単です。たとえば、省エネルギー機器の開発のためには有効な手段です。 Step 3:インパクト評価 インベントリー分析で得られた結果から、次に環境影響項目ごとに影響の度合い(インパクト)を評価します。一般的に行われるのは、エネルギー消費、地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、大気・水への排出、有害廃棄物、海洋汚染、森林破壊、砂漠化、生物種の減少……などの環境影響カテゴリーごとにわけて、環境への影響を集計する手法がとられます。現在は、オランダのエコインジケーター、スイスのエコポイントなどが有名な方法です。しかし、原因と因果関係の数値化などがむずかしく、より精度の高い分析方法の開発が必要とされています。 Step 4:結果の解釈 インベントリー分析や、インパクト評価をそれぞれ、あるいは総合で評価し、解釈します。LCAを行った目的とその範囲を確認し、改善や、判断のアクションを起こします。 |
| ■ライフサイクル・アセスメントの手順 |
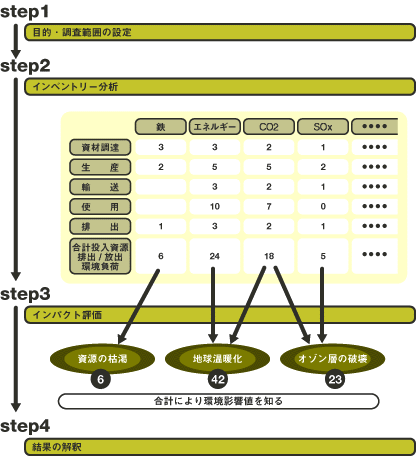
|
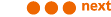 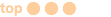 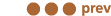
|