
|
エコデザインを実践する |
| 私たちの生活は、製品やサービスを提供する企業によって支えられています。企業が、環境に配慮した製品やサービスを提供するようになれば、最もてっとりばやく[循環型社会]を構築できると考えられます。単純にいえば、製品やサービスの[環境効率]を上げればよいわけですが、具体的には、どのように製品やサービスをデザインすれば、環境効率を上げることができるのでしょうか。 |
| 環境によいデザインとは |
|
エコデザインの詳細については諸説があり、2000年に入り議論はますます活発になってきていますが、環境庁、平成10年度環境白書『環境効率性の考え方』に即して手法をあげると、以下のことが考えられます。
1)投入する資源、エネルギーをなるべく少なくする 再生資材を使ったり、容器や部品を[リユース]したりして、なるべく自然環境から採掘する資源を少なくする。また、エネルギー効率を上げて、製造過程、運搬にかかるエネルギー投入をなるべく少なくすることも考えられます。 2)環境中に排出される環境負荷物質をなるべく少なくする 有害物質は、使わなくてすむなら、使わない。どうしても使わなくてはならないのなら、完全リサイクルさせる。冷蔵庫などに使われるフロンなどが、この例です。ダイオキシンのような有害性が高い物質は、完全に排出を止めなくてはなりません。即効的な有害性はなくても、二酸化炭素のように地球の温暖化を促進してしまうような物質は、排出を抑えるように努力しなくてはなりません。 3)使用段階における環境負荷を減らす工夫 洗剤なら、合成化学物質を使わない。自動車や家電製品のようにエネルギーを大量に使用するものは、省エネ設計をする。また、パッケージなどは、軽量化、あるいは使用後に減容化できるようにして、物流時の負荷を減らすように工夫する必要があります。 4)リユースやリサイクルのための設計 リサイクル可能な資材を使う。また、いろいろな素材で構成される製品は、解体分別しやすいように、接合部を工夫したり、ネジなどの部品を減らす。規格を標準化して、他社製品と互換性をもたせる。回収、運搬を容易にする設計をする。家電などのリサイクルのため、業界で、部品の共有化や、素材の情報を浸透させ共有する手法を考える、などがあげられます。 |
| 最終的には、製品のサービス化が目標 |
|
大量生産、大量消費型の経済システムのなかでは、消費者にくりかえし新品を買ってもらうことが利益につながりました。しかし、循環型の経済社会では、製品をなるべく長く使ってもらい、製品の長寿命化を図ることも、資材の無駄をなくす手だてです。そのために、製品の耐久性の向上も必要です。修理の利便性も考えなくてはなりません。
製造された製品を完全に回収して、[リユース]、リサイクルすることができるようになると、消費者は買った製品を“所有”するのではなく、製品が提供する“サービス”を買い、古くなって使えなくなったら、再び製造者にもどすという製品の循環が生まれます。メーカーが提供するのが製品ではなく、“サービス”であるという概念を、製品の“サービス化”、あるいは[脱物質化]と呼びます。 すでに、事務所で使うOA器機やコピー機はリースが主流です。車をリースしたり、共同所有するシステムもあります。大形の家電製品などでも、リースやレンタルの手法を取り入れていくことが可能です。こうして、消費者は、物質のコンシューマーからユーザーになり、メーカーは“サービス・プロバイダー”になっていくと思われます。 |
| ■環境設計を実現する製品設計の例 |
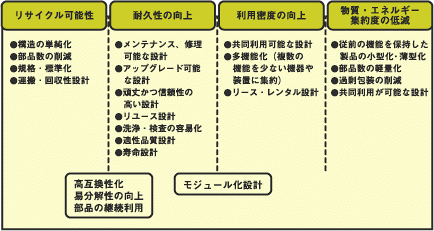
|
|
資料:環境庁 [出典]『循環型経済のしくみがよくわかる』 |
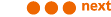 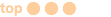 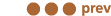
|