|
夏ばて予防
夏の暑さからくる体調不良はまとめて夏バテといわれ、 夏バテの症状は多種多様です。夏バテにふくまれるものとして、 気温の上昇や運動による体温の上昇、発汗による脱水症状、 食欲減退による栄養バランスのくずれ、睡眠不足、寝冷えによる夏カゼや オフイスでの冷房病などがあります。熱帯地方の住民では、 いわゆる夏バテという言葉がないそうです。ということは、 夏バテの予防はいかに暑さになれるかということになります。 |
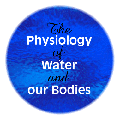 |
|
夏ばて予防
夏の暑さからくる体調不良はまとめて夏バテといわれ、 夏バテの症状は多種多様です。夏バテにふくまれるものとして、 気温の上昇や運動による体温の上昇、発汗による脱水症状、 食欲減退による栄養バランスのくずれ、睡眠不足、寝冷えによる夏カゼや オフイスでの冷房病などがあります。熱帯地方の住民では、 いわゆる夏バテという言葉がないそうです。ということは、 夏バテの予防はいかに暑さになれるかということになります。 |
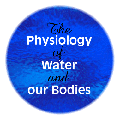 |
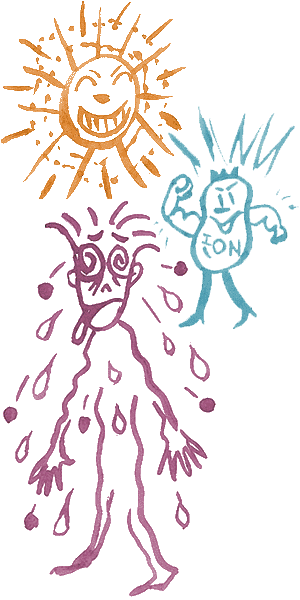 |
夏の食事 日本では夏になるとどうしても冷やしたソーメンなど、炭水化物を中心にした食事になりがちです。食事を摂ったあとにはその影響で代謝が上昇し、とくに肉などのタンパク質を摂ると代謝がより上昇します。そこで日本人は代謝の上昇の少ない炭水化物を摂り、体温の調節をしやすくしているわけです。しかし炭水化物の代謝にはビタミンBが必要です。同時にビタミンも補給できるようにバランスの取れた食事を心がける必要があります。熱帯地方では、カレーや唐辛子など、香辛料をもちいて味覚を刺激し、バランスの取れた食事をしています。 脱水による夏バテ 夏の暑さに適応するためには、うまく体温を調節する必要があります。体温の調節は皮フに流れる血液の量を調節し、皮フの温度を変化させておこないます。また環境温が30℃を超えると、皮フ血流量の調節だけでは体温を一定に保つことができず、汗によってからだの表面から熱を放散させます。人は発汗能が大きく、ほかの動物にくらべて体温を調節する能力がひじょうに大きいのですが、発汗による水分の喪失量は1時間に約2リットルにもおよぶことがあります。 この水分を十分補うことができない場合には脱水状態になり、いわゆる夏バテのいろいろな症状が見られます。脱水による1%の体重減少は体温を約0.3℃上昇させ、心拍数も1分あたり5〜10拍増加します。これら体温および心拍数の変化は体重の減少と関係しますので、水分を摂取すれば体重の減少は少なくなり、体温および心拍数の上昇がおさえられます。 しかし水負債が4〜6%におよぶと血液の量、唾液や尿の量が減少し、血液が濃くなり、心拍数・呼吸数・体温が上昇し、ノドの渇きも著しくなります。5〜10%以上の水不足で、激しい疲労感が起こり、精神身体機能も低下し、熱射病により死亡することもあるので、水分を補給することが重要です。 水分とイオンの補給 体液のうちほぼ5%が血液のなかの水分で、そのイオン組成はほぼ0.9%の食塩水です。いっぽう汗には0.3〜0.5%の食塩がふくまれ、1リットルの汗をかくと3〜5グラムの食塩が失われます。この際、水だけを飲むと血液が希釈されて口渇感がなくなり、またよぶんの水分を尿から排泄します。したがって発汗時の水分補給には汗から失われたイオンの補給が必要です。夏場には、生活のなかで意識的に水分とイオンを補給するように心がけるべきです。 |

|