|
からだの中の水分と体温
からだの中の水分量が減少することを、脱水といいますが、 脱水が起こると脱水熱といって体温が上昇します。 とくに小児や高齢者では脱水が起こりやすく、注意が大切です。 |
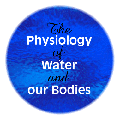 |
|
からだの中の水分と体温
からだの中の水分量が減少することを、脱水といいますが、 脱水が起こると脱水熱といって体温が上昇します。 とくに小児や高齢者では脱水が起こりやすく、注意が大切です。 |
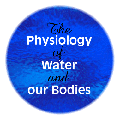 |
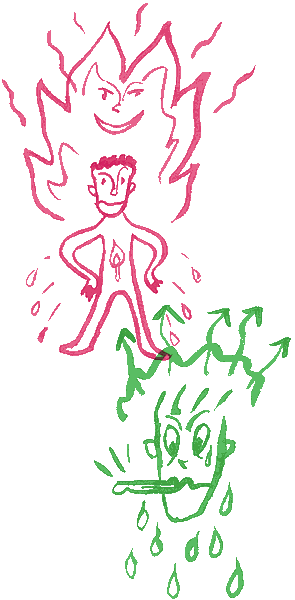 |
体重2%以上の脱水に注意! 脱水の程度が体重の2%程度までは、体温はほとんど上昇しませんが、体重が2%以上減少すると、体重減少1%ごとに体温が0.3℃ずつ上昇します。体重が60kgの人では、1.2kg以上脱水が起こると体温が上昇するわけです。 皮フからの熱の放散 それではなぜからだから水分が失われると、体温が上昇するのでしょうか。われわれのからだは、体温が上昇すると、皮フの血管を拡張させ、皮フから環境へ熱を逃がします。お風呂に入ったあとなど、からだが赤くなってほてった感じがするのは、皮フの血管が拡張し、熱を放散しているからです。 汗の打ち水効果 さらに体温が上昇すると、今度は汗を出し、汗が皮フの上で蒸発するときに熱を奪い、体温の上昇をくい止めてくれます。注射のときにアルコールで皮フを消毒しますが、そのときに皮フに風を送ると涼しい感じがするのは、アルコールが蒸発するさいに気化熱を奪うからです。このように、汗は皮フの表面にみずから打ち水をして体温を調節しているわけです。 脱水状態での体温上昇 ところが脱水状態では、運動時に筋肉を流れる血液量を確保する必要から、体温が38℃以上になると、皮フへ流れる血液がそれ以上増加しなくなり、体温がますます上昇します。同様に、発汗量も低下して体温が上昇します。水を飲むと汗の量が増加し疲れるので、水を飲んではいけないといわれることがありますが、これは脱水状態で汗が抑制され、体温も上昇していた人が、水分を補給したために汗がでやすくなるためです。 水分を充分補給し、脱水状態にならないよう気をつけていると、効率的に体温が調節され、体温の上昇も抑えられ、運動も長くつづけられることが実験的に証明されています。 |

|