
|
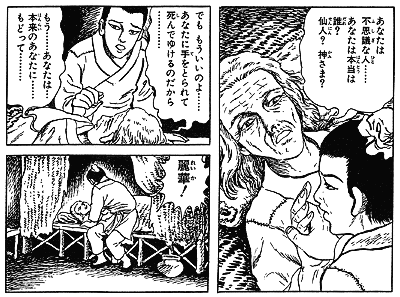
|
|
高野文諸星大二郎『無面目』 【引用図版・2】 『無面目・太公望伝』潮出版社89年刊・所収 169頁 |
|
『無面目』に登場する、こののっぺらぼうは、別名を混沌。 天地開闢(かいびゃく)から深い瞑想を続ける神という設定である。 ふとした疑問から神仙が顔を描き入れ、それによってはじめて無面目は語りはじめる。 《私はもともと太極が本質的に内蔵していた純粋な智の一部なのだ》 《へたに目で見ようとする者こそ 物事の真実を見誤るのだ》 しかし、目鼻をえた無面目は外部に興味をいだき、下界におりる。 そこで、食べることを知り、欲望を知り、陰謀をおぼえ、忘却をそなえ、都の政争に荷担し、やがて恐怖と愛を知って、ついに自分が何者であるかと問いながら悶死する。 人となってはじめて死をうるのである。 もはや神であることを忘れた無面目は、愛した女が老いて死ぬのを、自分は若いまま見送ることになる[図2]。 老死は、人間の身体の自然現象であり、それを超越することは、愛憎を知る人間にとっては不幸なことだと、この物語は語る。 たぶん、日本人を含む東アジアの人々にとって、こうした考え方はなじみ深いものではないかと思う。 人間が必然的にもってしまう智の力と、外界としての自然、老死という身体の自然、人間のさだめとしての自然が、矛盾はするけれど、結局はそこにかえってゆくのがまっとうなのだ。 いや、そもそも“自然”は、人の智が認識する概念で、それを外界、身体、運命と腑分(ふわ)けするのも智の便宜である。 東アジアの古い考えからすれば、これらは違うようにみえて、じつはみな同じ構造をもち、同じ因縁でつながっていることになる。 そして、智によって腑分けされ、認識される以前には、ただ目も鼻もない混沌があった。 さらにいえば、その混沌そのものにも本質的な智を認める。 これが諸星大二郎のマンガのいわんとするところであり、おそらく東洋の智とはそういうものなのだろう。 |
