 |
 |
|
毎朝、近くの公園にいって太極拳の練習をしている。保育園のとなりの公園なので、ときおり園児が集団で遊んでいて、私の練習にたかってくる。 “おじさん、ヘンな人?” “なにそれ、なんの踊り?” 中腰になってじっとしている練習中に背中に登ってくるのはいるわ、一緒になって“踊り”をまねしてきゃあきゃあ笑うのはいるわ、ついに鬼ごっこの鬼にまでされてしまう。 さほど子ども好きでもなかった私だが、歳とともになんだか幼児とたわむれるのが楽しくなってしまったらしい。 良寛か、わしゃ。 いや、そういう話じゃなかった。 最終回だから“自然”とはなにかって話をしようと思ったのだった。 連載の最初に書いたように、今、大多数の人々にとっての日常的自然は都会の片隅の公園だったり、植木だったりする。 非日常的自然は、交通の発達で熱帯のジャングルから砂漠、雪を冠する山、透明度の高い海、どこにでもいくことができるが、あくまで観光としての自然である。 私にとって、いちばん身近な自然は、いうまでもなく自分のからだである。 それを自然としてあつかい、制御し、またおうかがいをたて、無理なく動くように気を配ること。 太極拳をやったり、週1回水泳教室に通ったりするのは、結局は歳とともにそういったノウハウが重要になってきたからだ。 ところが、太極拳にしてもヨガ、気功にしても、やっていくと、いったいどこまでが自分の意思(意識)で、どこからが自然(身体)なのか、どんどんわからなくなる。 まるで、のっぺらぼうな、どっちつかずの領域がそこにある。 諸星大二郎『無面目』を読んだとき、そこにいる無面目は、まさにそうした意識とからだの境界領域、薄明の場所の擬人化にみえた[図1]。 |
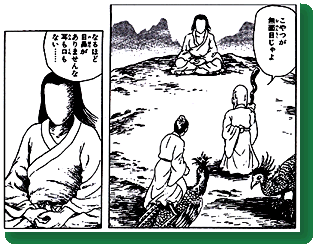
|
諸星大二郎『無面目』 【引用図版・1】 『無面目・太公望伝』 潮出版社89年刊・所収 15頁 |

|