NN:一度組み立てたモノを、解体して分別するのは容易なことではないですね。しかも、コンピュータはいろいろな素材が組み合わさっているから、素材の処理委託も大変ですね。
IBM:リサイクルの基本は分別です。私たちのセンターで分別しているのは、70種類以上。だから、製品設計の段階でのリサイクルへの配慮は大切です。IBMの環境配慮製品設計もすばらしいですよ。ぜひ次は、そのあたりを取材していただきたいですね(笑)。
処理委託業者についても、事前調査、現地調査、評価・判定を毎年繰り返すことにより、最も最適な処理業者を選び出しています。
NN:リサイクルの手法も、時代とともにどんどん進化していますよね。
IBM:リサイクル・センターは1968年の開設以来、30年間にわたって、継続的な環境負荷の削減、再資源化に取り組んできました。処理を委託する業者の再資源化技術も、どんどん向上してきています。
たとえば、プラスチックは95年まで埋め立て処理されてきました。その後、処分場の残余年数が問題となり、95年からは焼却しました。しかしダイオキシンが問題となり、現在は鉄鋼メーカーの高炉還元剤、あるいは樹脂としてリサイクルしています。
NN:スクラップのリサイクル量と、リサイクル率はどうなのでしょうか?
IBM:藤沢と野洲に入ってきた廃棄物の重量でいうと、1996年の7,120トンをピークに年々減少し、99年には5,893トンになりました。これは、コンピュータが技術革新により小型軽量化していることと、中古市場が拡大したことに起因します。
一方、リサイクル率でいいますと、年々向上し、2000年11月の実績で98.1%です。あとの約2%は塩化ビニル関係です。しかし、今度このような取材があったら、そのときには再資源化率100%を達成していると思いますよ!
NN:それは楽しみですね! 本日はお忙しいなか、ありがとうございました。
“リデュース、リユース、リサイクル”……環境経済のコーナーがはじまってからこの1年間、何度となく、聞いたり、語ったりしてきた資源削減のための合い言葉です。IBMでは、製品設計の段階で使う資源の量を減らし、リユース・センターで製品・部品を修繕して再利用し、最終的にリサイクル・センターで素材のリサイクルをしています。
はからずも、このコーナーのひとまずの最終回で、この“3つのR”のお手本を見せていただくことになりました。
2001年4月からは、[資源有効利用促進法]が、施行されます。パソコンもその適用を受けることになり、リサイクルに加えて、廃棄物の発生抑制、修理、部品の再利用、製品の回収などが義務づけられます。今後、企業向けに販売(売却)されるパソコンの回収方法は2001年に向けて計画中であるものの、藤沢リサイクル・センターをみるかぎり、IBMはこういった機能をすでに完成させているようです。
“ローカルな法律の一歩先を行く、コーポレート・スタンダード”……前回の取材で、日本IBMの環境担当次長・岡本さんがおっしゃっていた、この企業の理念を、まさに実感させられた取材であったことを、最後につけ加えておきたいと思います。
|
|
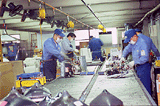
|
(リサイクル・センター)
廃棄パソコンやモニターを人手で分解
|

|
(リサイクル・センター)
これがお宝の山! パソコンのカード類には、貴金属が多く使われている
|

|
(リサイクル・センター)
ノートブックの液晶画面の裏にはこんな蛍光管が
|

|
(リサイクル・センター)
抜き取られた電池類
|
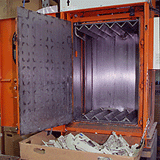
|
(リサイクル・センター)
ケースなど、プラスチック部品を破砕する破砕機
|
|


