
|
そして、フロー経済から、ストック経済へ |
| フロー経済? ストック経済? |
|
経済学的にいうと、一定期間で新たにつくり出された付加価値の合計をフローといいます。国民総生産(GDP)は、この付加価値の1年分にほぼ相当します。一方、ストックとは、住宅総戸数、自動車の保有台数、預金残高など、経済財の存在量のことをいいます。
戦後、日本は焼け野原になり、ストックが極端に不足しました。このストックを充実させるためには、1年に消費されたり、減価償却される分を上回る量で、フローを急速に増やせばよいわけです。これが、戦後、日本がとり続けた経済政策であり、高度経済成長の実態でした。 1970年代には、戦争で失われた住宅、道路、鉄道などの社会ストックも回復し、日本は世界第2位の経済大国になりました。反面、豊かな自然環境は失われ、公害問題が発生し、狭い家にモノがあふれ、人々は仕事に追われて、生活を楽しむ余裕すらありません。 フロー経済では、生産性が重視されますから、消費される資源も、エネルギーも、生産量に比例して大きくなります。結果、資源の枯渇問題、温暖化など、地球規模の問題が発生するようになってきました。 ストックを回復した日本にとって、これから重視すべきはフローを増やすことではなく、ストックを維持し、その質を高めることです。 |
| 新しい“豊かさ”の基準を! |
|
GDPという指標そのものが、フローの経済を基本に、“毎年これだけ生産した”という指標ですから、この考え方で私たちの“豊かさ”を測ることを、そろそろやめなくてはなりません。美しい自然・住環境、高度な文化……こうした生活の“質”を計る指標をもって、私たちの豊かさの基準にしなくてはならないでしょう。
ストック重視型の経済では、 大量生産・大量消費に代わって、適正生産・適正消費を目標とします。モノを使い捨てるのではなく、何度も繰り返し使い、製品も長寿命化することが必要になります。住宅、鉄道、道路、自動車、家電など、これ以上の総量を増やさないで、買い換え、修理、更新、メンテナンスに重点を置くわけです。 “モノを作らないなら、なにを売ればいいのか?”“それじゃあ稼げないじゃないか”と、不安になる方もいらっしゃると思います。それに代わるのが、メンテナンスサービス、設計、アイデア、著作活動、コンセプトなどの無形財です。 |
| そして、21世紀! |
|
私たちはいま、未曾有の不況と深刻化する環境問題、一見相容れない問題を抱えこんで立ち往生しているようです。なす術も見つからないまま、政府は従来の公共投資による景気対策により、財政赤字をふくらませてもいます。こういった状況を称して、1990年代を“失われた10年”と呼ぶ人もいます。
環境対策と経済不況の新たなる解決策は、じつは同じ方向にあるのではないでしょうか。しかし、この新世紀の経済体制が完成するまでには、私たちは多くの変換を迫られるでしょうし、意識の変換から生活様式の変換まで、多くの産みの苦しみもともなうはずです。 1つはっきりしていること、それは、1990年代が、環境問題をグローバルにとらえるようになった10年間だったということです。 日本でも2000年には、環境6法が成立し、2001年からあいついで施行されます。環境重視の21世紀型・経済社会の構築が現実のものとなれば、1990年代は“失われた”のではなく、新たな展望が開けた10年だった……そのとき、きっとそう言えるのではないか、私たちはそう考えています。 来月は、[環境と経済]世論調査!のコーナーに、みなさまからお寄せいただいた貴重なお答えを集計して、“世論調査の結果”をご報告します。乞うご期待! |
| ■フロー重視とストック重視の経済社会のちがい |
|
| [出典]日本経済グリーン富国論 |
|
[参考資料] 『日本経済グリーン富国論』 三橋規宏・著 東洋経済新報社・2000年刊 『平成12年版・環境白書』 環境庁・2000年刊 『地球環境経済人サミット講演資料集』 日本経済新聞社・主催講演資料 2000年刊 『ディジタル・エコノミー2000 米国商務省リポート』 米国商務省・著 室田 泰弘・編訳 東洋経済新報社・2000年刊 |
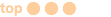 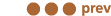
|