
|
地方からはじまる環境運動 |
| 琵琶湖の赤潮からはじまった、1つのプロジェクト |
|
1977年5月、滋賀県の琵琶湖で赤潮が大発生しました。琵琶湖は、京都、大阪、兵庫など、近畿地方に住む1,400万人が飲み水として利用している水源です。赤潮の原因の1つが、合成洗剤に含まれるリンであることを知った滋賀県の一部住民は、合成洗剤の使用をやめて石鹸を使う運動を開始しました。
この活動に参加した住民は、リンの使用禁止を訴える一方で、琵琶湖の水を汚す原因になっている廃食油を回収して石鹸を作るシステムをつくりあげました。1980年には県に働きかけ、洗剤にリンの使用を禁止する、“琵琶湖富栄養化防止条例(通称せっけん条例)”を制定させるにいたりました。1990年には知事の認可を受け、滋賀県環境生活協同組合(通称“環境生協”)を設立。住民運動を組織的に強化しました。 ところが、せっけん条例に対応するために、メーカーは“無リン”の合成洗剤を発売し、環境生協は大量の廃食油をかかえ、回収システムも存亡の危機に立たされました。 だぶつく廃食油に困っていた環境生協に、耳寄りな情報がドイツから届きました。ドイツでは、枯渇資源である石油に頼らず、しかも二酸化炭素の排出量を抑えることのできる、菜種油を代替燃料として使うプログラムが進んでいたのです。 環境生協は、行政や研究所に働きかけ、滋賀県愛東町にBDF(バイオ・ディーゼル・フューエル)プラントを設置。今度は、廃食油をディーゼル燃料として利用するシステムをつくりあげました。 |
| “菜の花エコプロジェクト”、スタート |
|
1998年には、廃食油を利用するだけでなく、菜種を転作田にまき、搾った菜種油を学校給食で使い、その廃食油を石鹸や燃料に精製するという循環システム、“湖国 菜の花エコプロジェクト”をスタートさせました。滋賀県もこの構想に賛同し、県としてこのプロジェクトを推進していく方針を明らかにしました。
菜の花エコプロジェクトで注目すべき点は、自分たちの住む環境を守るために、住民が自ら立ち上がって行動したこと、住民、行政、民間が一体となって活動していることです。また、こういった地域ぐるみの活動は、その地域の活性化にもつながり、独特の自然や文化を守ることにもなるのです。 滋賀県の菜の花エコプロジェクトは、地域を核とした環境活動の一例にすぎません。全国で、自らの地域を守るために多くのプロジェクトが立ち上がりはじめています。その活動を紹介するホームページを、以下にいくつかご紹介します。 |
| ■湖国 菜の花エコプロジェクト・マップ |
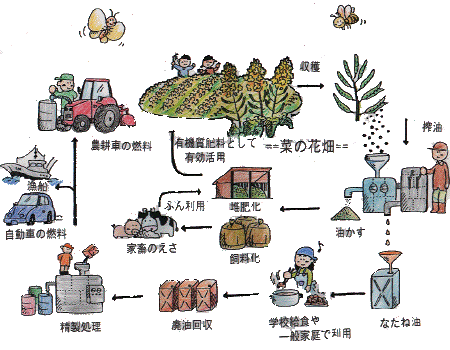
|
|
[出典]環境生協
環境生協ホームページ 菜の花プロジェクトの主体 http://www.econavi.or.jp/ RENET WEB 早稲田商店会によるリサイクル活動 http://www.re-net.info/ 熊本県水俣市HP 公害の町から環境の町へ、日本一の資源ゴミ分別回収 http://www.minamatacity.jp/ 藤前干潟 藤前干潟の埋め立てを断念し、ゴミ減量都市に挑戦する名古屋市 http://www.kankyo-net.city.nagoya.jp/fujimae/ |
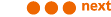 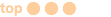
|