
|
日本ではどうなっている? |
|
京都会議で決定した削減目標を達成するためには、日本でも思い切った対策を早急にとらなくてはなりません。
政府税制調査会では、炭素税などの税金などによる環境負荷削減対策を検討しています。2000年7月の答申では、ガソリンなど排出源が多い場合には、税金による対策が有効であり、OECDが定めた[汚染者負担の原則:PPP]という意味からも、二酸化炭素の排出者、つまり燃料の消費者が、対策費を負担することを基本に考えるべきであるとしています。 図表からもおわかりのとおり、日本での二酸化炭素の排出量は、民生部門、運輸部門において増加しており、そのなかでも自家用車の排出量が55%を占めています。しかし未曾有の不況下にあって、自動車産業が日本の経済に対し果たしている役割を無視するわけにもいきませんし、石油価格が上昇することによる経済への影響も考えなくてはなりません。 日本の自動車にまつわる税金は、多岐にわたり、取得段階で消費税と自動車取得税、保有段階で重量税と自動車税、走行段階で揮発油税、地方道路税など複雑で、すでにかなりの重税です。この税制度を整理し、相互の整合性をもたせること、省エネ仕様の車両には税の軽減策をあたえるなど、従来の道路整備などの資金としてだけではなく、環境税としての視点を加えることが必要でしょう。そして、それらの点をふまえ、早急に対策を検討しなければならない時点にきていることは、事実のようです。 温室効果ガスの削減問題は、一国だけの問題ではなく、地球全体で早急に対処しなければならない緊急課題です。日本が率先して思い切った施策を実行し、これから工業発展を遂げるであろう国々に先鞭(せんべん)をつけることは、京都会議の議長国の果たすべき役割です。また、ほかの国に先がけて省エネ製品を開発すれば、環境を改善できるのみならず、自動車、家電製品の国際競争力を高める効果もあるのではないでしょうか。 2000年5月、石広 光・一橋大学学長をを座長とする環境庁の検討会では、以下のような試算がなされました。 炭素税のみで、2010年までに1990年比で2%二酸化炭素を削減することを目標とすると、炭素1トンあたり3〜4万円(ガソリン1リットルあたり20〜26円)の税金となります。しかし、炭素税、排出権取引、省エネ促進補助金などのポリシーミックスにより、炭素1トンあたり3千円(ガソリン1リットルあたり2円程度)でも同じような削減効果をあげることができ、経済への影響も少ない、というものです。 炭素税が導入されると、ガソリン、燃料、電力料金などに微妙な値上がりが予想されます。しかし、この税金は、地球環境と引き替えと考えてみれば、安いといえるのではないでしょうか。省エネ対応製品、エコカーの需要も、いま以上に増していくなどのメリットを加味して、じっくりと考えてみるべき問題であると思います。 |
| ■輸送機関別にみた二酸化炭素排出量(1997年度) |
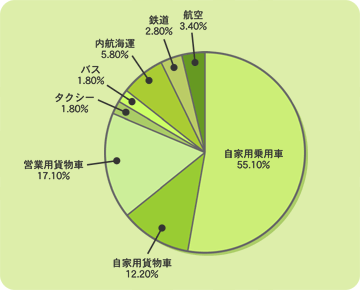
|
|
[資料]運輸省 [出典]平成12年版『環境白書』 |
| ■輸送機関別にみた二酸化炭素排出量原単位 |
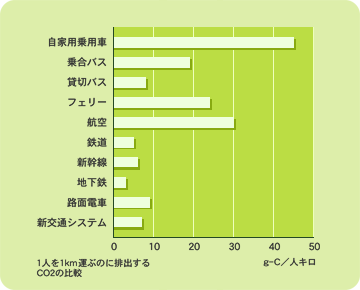
|
|
[資料]地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同資料
[出典]平成12年版『環境白書』 |
|
[参考資料] 平成12年版『環境白書』 環境庁・2000年刊 『日本経済グリーン国富論』 三橋 規宏・著 東洋経済新報社・2000年刊 『エコプロダクツガイド 2000』 日経BP社・1999年刊 |
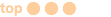 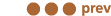
|