
|
逆工程を入れる:インバース・マニュファクチャリング |
| 逆工程を製造工程に組みこむ |
|
ゼロエミッションが、他企業などに廃棄物を資源として利用してもらい、別の用途で廃棄物を循環させるのに対して、[インバース・マニュファクチャリング]は、従来の生産活動の生産 → 使用 → 廃棄という“順工程”から、逆に回収 → 分解・分別 → 再利用 → 生産の“逆工程”を生産システムに入れて、同じ製品のライフサイクルのなかで循環させることをいいます。
もっともわかりやすい例は、フィルム会社が発売しているレンズ付きフィルムです。フィルム会社は撮り終わったカメラからフィルムを回収して現像し、カメラ部分はまた製品に利用しています。レンズ付きフィルムは発売当初、“使い捨て”のイメージが強かったのですが、現在ではリサイクルセンターに回収した製品を、機種ごとに仕わけし、分解しています。 レンズとストロボがはずされて、品質検査を通ったもののみが、洗浄などの処理をほどこして、ふたたび利用されています。このように、逆工程を考えて製造工程が設計されていることが、インバース・マニュファクチャリングのもっとも肝要なところです。 インバース・マニュファクチャリングは、吉川 弘之・前東京大学学長が提唱し、産業界、とくにメーカーで、これを取り入れて生産設計をおこなう企業が増えてきています。 |
| ■インバース・マニュファクチャリング(逆工場)の概念 |
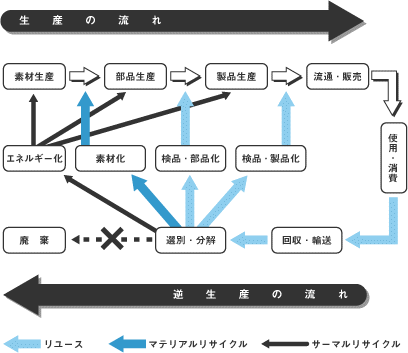
|
|
出所:日刊工業新聞 出典:『地球環境ビジネス2000→2001』 |
| 家電リサイクル法の施行を前に、対応を急ぐ家電業界 |
|
製造時に発生した余剰物や使用済み製品を、同一の製品群のなかで循環させれば、原材料や廃棄物の量がはるかに少なくてすみます。とくに、2001年4月に施行される[家電リサイクル法]により、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機のリサイクルが義務づけられる家電メーカーでは、早急な対応が必要です。
製品をそれぞれのメーカーにもどせば、回収、分解の段階で無駄ができますから、業界全体で[リサイクル工場]などを建設することを視野に入れて対策を講じなければなりません。そのためには、各メーカーの製品の、設計から流通、使用、廃棄にいたる“環境情報”を、メーカー、流通業者、回収業者、処理業者のあいだで共有化する必要があります。 96年吉川 弘之氏を会長にして、産業界、大学関係者、国立研究所、地方自治体、通産省などにより、“インバース・マニュファクチャリング・フォーラム”が立ちあげられました。製品情報システムのプロトタイプモデルを作成し、デモンストレーションをおこない、ホームページを利用して製品の環境情報共有化のための下地をつくっています。 ◎インバース・マニュファクチャリング フォーラムのHP http://www.mstc.or.jp/inverse/main.htm |
| ゼロエミッションやインバース・マニュファクチャリングを達成するということ |
|
資源を循環させることによって廃棄物をなくす、というゼロエミッションは、自然環境のなかでは“ごくあたりまえに”成立しているものです。また、江戸時代の日本では、ゼロエミッションが日常生活のなかで成立していたとされています。
ゼロエミッションを達成するためには、資源を大切にしようという意識をもつ必要があります。それだけではなく、資源を有効に活用してくれる受け入れ先や技術をさがすために、情報も必要です。そして、物質を循環させるクラスターのなかでは、共同体意識も欠かせません。また、インバース・マニュファクチャリングを実行しようと思えば、いままでは閉鎖的だった企業間の情報を公開しなければなりません。 ゼロエミッションやインバース・マニュファクチャリングに関する文献を読み進むうちに、廃棄物をなくす努力が、人間の交流の場を提供していることがわかってきます。リサイクルを進めるうえで、関係する企業や住民が納得して参加しているということや、お互いに協力しあうためにコミュニケーションをとるということが、必要不可欠になってくるからです。 ゼロエミッションやインバース・マニュファクチャリングは、使い捨ての時代に私たちが気がつかずに捨ててきてしまった、“人の輪”をふたたび構築する作業でもあるようです。 |
|
[参考資料] 『ゼロエミッションと日本経済』 三橋 規宏・著 岩波新書・1997年刊 『地球環境ビジネス 2000→2001』 エコビジネスネットワーク・編 産学社・1999年刊 『循環型経済のしくみがよくわかる』 グリーンマーケティング研究所 中経出版・2000年刊 『日経エコロジー エコプロダクツガイド2000』 日経BP社・1999年刊 |
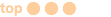 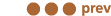
|