
|
廃棄物は出さない:ゼロエミッション |
|
資源の採取 → 生産 → 使用 → 廃棄という資源の“一方通行”を変えて、循環型の経済構造を構築する……そのために、私たちは、なにをすればよいのでしょうか。
92年のリオ地球環境会議以来、[循環型経済]を実現させる手法が研究されるようになり、国連大学が提唱した[ゼロエミッション]、日本で発案された[インバース・マニュファクチャリング]が、いま注目を集めています。 |
| 国連大学による提唱 |
|
まず、物質を廃棄することをいっさいやめ、廃棄する物質を、むしろ生産の資源として活用しようという考え方が、[ゼロエミッション]です。もともと、自然界では捨てるものなどなにもなく、物質はすべて循環しています。動物の排泄物は植物の栄養となり、植物は動物のえさとなる、という循環がくり返されています。そういった循環を、産業構造にも応用しようというのです。
ギュンター・パウリは、自分の洗剤会社が、投入する資源のほんの一部しか使わず、その20倍もの廃棄物を捨てていることに疑問を抱き、資源のすべてを活用し、なにも捨てない生産設計を広めなければならない、と強く感じるようになりました。このパウリの考えは国連大学で受け入れられ、94年にZERI(Zero Emissions Research and Initiatives)が設立されました。そして、95年4月におこなわれた第1回ゼロエミッション世界会議で、公式にその概念が提案されました。 |
| ゼロエミッションによる循環の輪 |
|
“産業・A”が排出する廃棄物を“産業・B”の原材料に、“産業・B”が排出する廃棄物を“産業・C”が原材料に使う……どの産業でも廃棄物をゼロにすれば、物質は完全に循環します。つまり、集団のなかで、物質循環の“クローズドシステム”が生まれるのです。
排出される物質の多様性を考えると、廃棄物の受け入れ先もさまざまな業種にわたります。廃棄物=原材料というつながりを通して、産業集団(クラスター)が形成されるようになります。クラスターは、物流の合理性を考えると、当然近隣に集まっているべきですから、工業団地や市町村が、クラスターの基盤になります。ゼロエミッションを実現するには、クラスターを形成する地域全体で産業構造を考えたり、また、異業種間で情報交換をしたりすることが重要になってくるのです。 |
| 国連大学による試み |
|
ZERIは96年“ZERI基金”を設立し、世界中の気候が異なる地域で実証実験をおこなっています。フィジー、ナミビア、コロンビア、スウェーデン、日本などで、日本やドイツの企業の協力も得ながら、ビール生産、農業生産、廃棄物削減、町の開発などにおけるゼロエミッションの可能性を追究しています。
◎ZERIのホームページ ZERIの説明と、活動報告を見ることができます。 http://www.zeri.org/ |
| ■国や自治体のゼロエミッション事業 |
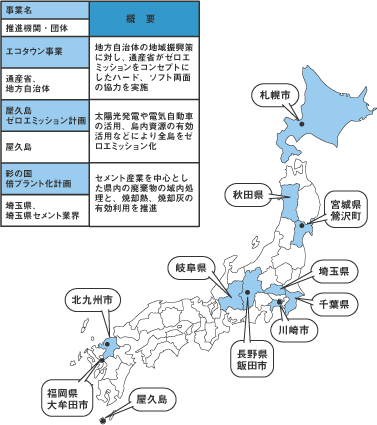
|
| [出典]『循環型経済のしくみがよくわかる』 |
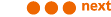 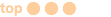
|