
|
利潤追求から社会的責任へ |
| 公害から環境問題へ |
|
第1回では、いままでのような大量生産、大量消費、大量廃棄型経済成長には限界があることを学んできました。第2回では、環境負荷を与える経済活動に“待った”をかける法規制をご紹介しました。 環境問題と法規制は、さまざまな企業にとって、以前には存在しなかった大きな“圧力”ですが、今後、企業はこれらの圧力と“折り合い”をつけていかねばなりません。一方で、企業活動を中心とした経済が私たちの生活を支えているのも事実ですから、私たちも、さまざまな企業の取り組みを注視していく必要があるのではないでしょうか。 |
| 社会的責任としての環境問題 |
|
20〜30年前に経営学を学んだ方は、企業の目的は“利潤の追求”であると教えられたと思います。しかし、企業が未曾有の繁栄を続けた結果、その社会的な影響力は無視できなくなりました。生産する商品やサービスが消費者に与える影響はもちろんのこと、地域社会との折り合い、公害問題など、社会の構成要素として責任を問われることが多くなりました。そして90年代、新たな社会的責任として、環境対策が企業に課せられることになったのです。
環境問題に限らず、企業が社会的責任を問われた場合、賠償・補償という形でコストが発生する可能性があります。企業活動が社会道徳に反する活動をしている場合、そのリスクは高まるわけです。 ある活動が環境に大きな負荷を与えかねないことを、[環境リスク]といいます。これだけ環境問題が切迫してくると、環境問題に対応できない企業は、将来的に大きな負担を背負いこむ、つきつめれば、存続できない、ということにもなります。公害など、直接責任を問われる場合もあります。しかし、それにとどまらず、消費する資源と排出する廃棄物を抑制し、その管理を徹底するなどの対応が遅れた企業は、この種の“リスク”を背負うことになります。つまり、環境を考えた“経営”が必須のものとなり、社会的責任は企業の収益に大きく影響し、それを果たせるかどうかで、企業の価値が問われるようになってきたのです。 |
| 企業活動すべての段階で環境負荷を減らす |
|
それではいったい、なにをどうすれば、企業活動から環境負荷を減らすことができるのでしょうか。最近は、“地球にやさしい○○”とうたった商品が目立つようになりました。企業の環境問題というと、環境にやさしい商品をつくりだせばよいと思われがちです。もちろん、そういった商品やサービスを開発することはもっとも重要です。しかし、企業が与える環境負荷はそれだけではありません。
◎製品の素材はリサイクル資源を使っているか ◎工場で省エネを実施しているか ◎廃棄物をなくし、リサイクルをしているか ◎リサイクルするのとバージン材を使用するのとではどちらが二酸化炭素排出量などの環境負荷が少ないか ◎輸送は合理的か ◎管理部門での省エネ・省資源は進んでいるか……などなど、企業活動すべてにおいて環境負荷を計測し、総合的に判断しなければ、ほんとうに“地球にやさしい”企業を選び出すことはできません。 |
| ■環境投資の経済への影響 |
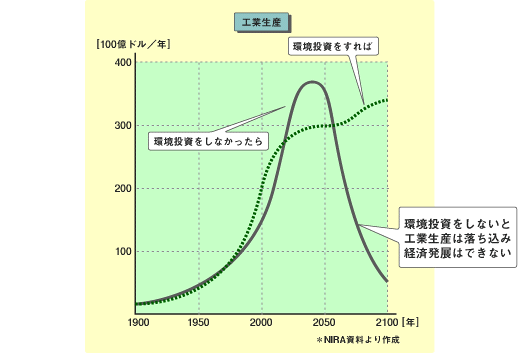
|
|
このまま環境問題を放置すれば、環境汚染が経済活動自体をもさまたげる。企業が環境投資をすれば、短期的には費用がかかったとしても、長期的に環境と調和するかたちで経済成長もできると考えられる。 [出典]『手にとるように環境問題がわかる本』 *NIRA研究報告書“地球環境政策のあり方に関する研究”(総合研究開発機構 平成7年9月28日発行)をもとにして作成 |
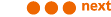 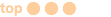
|