
|
法律が規定しているもの・2 |
| [家電リサイクル法] |
|
2001年4月から施行される、リサイクル関連法のもう一つの目玉が、[家電リサイクル法]です。テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の4品目に関して、小売業者、製造業者に回収、再資源化が義務づけられます。その際、消費者は廃棄の処理費用を負担しなければなりません。
家電各社では、リサイクルすることを前提に、資材や原料を調達するようになります。メーカー間での材料の共用化、資材情報の伝達などが重要な課題となり、リサイクルに便利な資材を供給できるメーカーは、大きなチャンスです。また、回収・廃棄の費用を消費者から受け取ることができますから、回収、分別などの“静脈ビジネス”も1つの市場を形成すると思われます。 |
| ■家電リサイクル法の概要 |
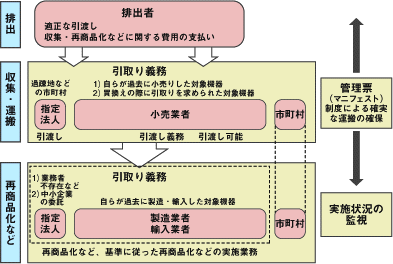
|
| [出典]環境庁/平成11年度環境白書 |
| [廃棄物処理法] |
|
[廃棄物処理法]は、91年にも改正されましたが、97年に再び改正、1年半をかけて段階的に施行されました。産業廃棄物をめぐる問題は、栃木県小山市の産業廃棄物処理業者が有害廃棄物をフィリピンに輸出した事件や、香川県豊島に50万トンの産業廃棄物が不法投棄された事件など、最近頻繁に問題になっています。
要するに、最終処分場の不足が顕在化してきているのです。そのため、廃棄物処理法は度々改正されてきました。今回の改正では、厚生省の認定を受ければ、廃棄物処理業や施設としての許可をとる必要がなくなりました。また、すべての産業廃棄物に対して[マニフェスト(積荷目録)制度]を導入するなど、不法投棄に対しては管理を徹底させました。 循環型社会においては、産業廃棄物は大切な資源です。生産者、廃棄物処理業者、新規参入業者が連携して、リサイクルの輪を確立しなければなりません。最終処分場の限界を考えると、早急に廃棄物を減らし、最終的にはゼロにすることが必要です。 |
| ■産業廃棄物の最終処分場の残余容量と残余年数(平成8年度末現在) |
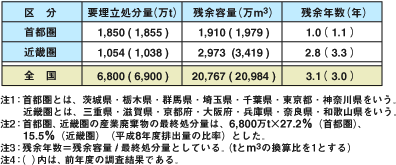
|
| [出所]厚生省 |
| そのほかの環境関連法 |
|
そのほかにも、以下のような環境に関する法律が、次々と制定されています。どれも、問題が多方面に影響するものだけに、複数の官庁が連携して、法案作成にあたっています。 [環境税] [環境汚染物質排出移動登録 PRTR法] [ダイオキシン類対策特別措置法] [食品廃棄物再資源化法案] |
| 法規制と規制緩和 |
|
最近の世の中の流れから、法規制を受けることには抵抗があると考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、このまま環境汚染を放置することはできません。新たな法規制が加わるとともに、現状にあわせて法の改正や緩和に踏み切ることも必要となるでしょう。大事なことは、目的をはっきりさせること、時代に即した法を、的確に作っていくことだと思われます。
しかし、押し寄せる環境問題に、対応が遅れがちなのが現状です。ペットボトルの回収、リサイクルなどのように、うまく機能しない場合もあります。環境問題は、大きな社会問題です。私たちひとりひとりが法規制の必要性を認識し、是非を決定し、運営に協力していかねば成り立たないのです。 [参考資料] 『地球環境ビジネス 2000-2001』 エコビジネスネットワーク編 産学社・刊 『日経エコロジー エコプロダクツガイド2000』 日経BP社・1999年12月刊 『日経エコロジ』 2月号 日経BP社・2000年1月8日発行 『日経ECO21』 3月号 日経ホーム出版社・2000年3月1日発行 |
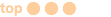 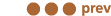
|