|
第26回
水で走る?……燃料電池自動車・その1 文/舘内 端 |
|
■水で走る自動車
世の中、進歩が激しい。ついに、水で走る自動車が現れた。しかも、10リットルの水で90km走るので、燃費というか水費というか、それは、リッター9キロである。けっして自慢できる燃費ではないが、燃料が水だと思えば、大いに納得できる。 もっとも、最近はガソリンや軽油よりも飲料水のほうが高いので、水で走る自動車の経済性は悪いのかもしれない。 水で走る自動車というのは、誤りではないが、すべて正しいわけではない。誤解されると困るので正確に説明すると、水から水素を作って、その水素で走る自動車である。つまり、最近話題の燃料電池車ということだ。 また、実際には水素を使うのだが、燃料が水であれば無尽蔵であり、かつ排ガスもCO2も出さないから、まさに人と自然と共生できる自動車ともなる。 ■燃料電池車の燃費 燃料電池は、水素と大気中の酸素を燃料として、電気と水を発生させる発電機だ。バッテリーのように電気を蓄えておくわけではなく、燃料が供給されたときに、その量に応じて発電する。 その原理は水の電気分解の逆である。ご存じのように水を電気分解すると、水素と酸素が生まれる。逆に、水素と酸素から電気と水を発生させるのが燃料電池である。 次世代車といわれる21世紀の自動車に関心のある方であれば、ここまではご存じだろう。しかし、燃料電池車の燃費となると、しかも、水何リットルで何キロ走るのかとなると、なかなかデータもなく、ご存じの方は少ないかもしれない。 燃料電池車の燃費は、エンジン車と同様に、クルマの性能で決まる。車体が軽くて、空気抵抗が少なく、効率の良い燃料電池とモーターであれば、もちろん燃費も良い。 実際には、容積が100リットルのボンベに水素を250気圧で詰めて、約180kmほど走れるといったところだ。 といっても、どの程度の燃費なのか、わかりにくい。ボンベの容積が100リットルといっても、中の水素は250気圧で圧縮されているし、気体だから、ピンとこない。果たして、この水素はどのくらいの重さなのだろうか。 ■水素2.2kgで180km 100リットルのボンベに水素(気体)を250気圧で圧縮して詰めるのだから、圧縮する前の水素は、 100×250=25,000リットル となる。 では、この水素は、どのくらいの重さのなのだろうか。 気体の重さを知るには、モルという単位(考え方)を使う。気体1モルは、22.4リットルであり、その重さは、気体の分子量で知ることができる。25,000リットルの水素は、 25,000 ÷ 22.4 = 1,116モル で、 水素(H2)の分子量は2だ。つまり、水素1モルは22.4リットルで、その重さは2gである。1,116モルの水素の重さは、 1,116×2 = 2,232g 約2.2kg となる。 したがって、100リットルのボンベを積んで、これに250気圧に圧縮した水素を詰めた燃料電池車は、たった2.2kgの水素で180kmも走ることになる。 ちなみに、ガソリン車では1リットルの燃料で20kmも走れば、相当に良い燃費であり、180km走るには9リットル必要で、この重さは約6.8kgである。 低燃費なガソリン車の3分の1の重さの燃料で走れるわけだから、燃料電池車とは、なんとも素晴らしい燃費の自動車ではないだろうか。ただし、気体の水素は2万5千リットルも使うのだが……。 ■水なら20リットルで180km走る さて、燃料電池車の燃料である水素はどうやって作るのだろうか。これにはさまざまな方法があって、水素の車体への搭載方法も含めて、これから論議がはじまるところだ。 水素の製造方法というか、原料には、石油、天然ガス、石炭などがある。日本では現在、燃料電池車を50万台走らせられるほどの水素が石油から生産されている。 あるいは、太陽光発電、風力発電、水力発電などの自然エネルギーによる発電で、水を電気分解することも、不可能ではない。これであればエネルギーは再生可能となり、自然とクルマの共生が可能だ。 ということで、ここでは水を電気分解して水素を作ることにして、それでは180km走るのに何リットルの水が必要なのか、計算してみよう。 1モルの水素は、1モルの水から作ることができる。180km走るのに必要な水素は、25,000リットルで、これは1,116モルであった。つまり、これだけの水素を作るには、1,116モルの水が必要ということになる。 ところで、水素と酸素からできている水の1モルの重さは、18gである。したがって、1,116モルの水の重さは、 1,116 × 18 = 20,088g 約20kg だ。 20kgの水の体積は20リットルだから、この燃料電池車は20リットルの水で180km走ることになる。その燃費ならぬ水費は、180 ÷ 20 = 9km、リッター・9キロだ。 はたして、この水費は良い燃費なのかどうか。よけいわからなくなったかもしれない。 ■頭を切り替えよう ところで、水素と酸素から電気と水を作る燃料電池は、逆に水を加えて電気を流すと水素と酸素を発生させることができる。水の電気分解にも使え、実際に利用されている。 そうであれば、燃料電池で水を電気分解し、水素と酸素を作って、その水素と酸素で燃料電池車を働かせ、クルマを走らせることはできないだろうか。 それは不可能なのだが、そんな錯覚に陥りそうである。次世代車のNo.1候補の呼び声の高い燃料電池車ではあるが、それを迎えるには私たちも大いに頭を切り替える必要がありそうだ。 [出典]三菱自動車HP ◎http://http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ECO/2_5.html |
■燃料電池車の概念図
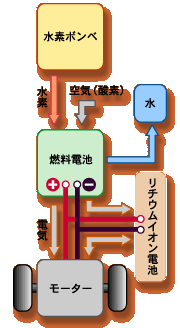
■三菱自動車で開発中! 三菱自動車が、99年の東京モーターショーに出展したMFCV(Mitsubishi Fuel Cell Vehicle)。この例では、取り扱いが比較的容易なメタノールを用い、積載した改質器で水素を発生させ、燃料電池に供給するシステムを採用。これらをごくコンパクトにまとめ、床下に収納することにより、広い居住空間・荷物スペースを確保している。 
キュート! すぐにも乗りたい! 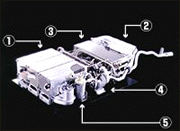
1)燃料電池 2)燃料タンク 3)改質器:燃料タンクからのメタノールを用い、ここで水素を生成 4)補機(圧縮機等) 5)水タンク |