■クルマと遊び
人と物を運ぶ便利な運搬具としてばかり強調される自動車だが、自動車にとって遊びの要素も大事だと思う。だが、いざクルマ遊びとなるとはたと考えこんでしまう。
ロジェ・カイヨワは、遊びには“競争”“偶然”“模倣”“めまい”の4つの機能があるという。ちなみに、ロジェ・カイヨワはフランス生まれの社会学者であり、思想家であり、哲学者であり、20世紀の偉大な知性だ。
自動車は、まず運搬具として大変に重宝だ。多くの人から愛されるのも、この便利な運搬具としての自動車である。しかし、“物運び”遊びというのも、なんだか変だ。RVは、レジャービークルだから遊びクルマだが、それにサーフボートやスキー板、キャンプ用具を載せて遊びに行くには便利としても、RVそのものを“遊ぶ”人はいないだろう。
■走る、走る、走る
クルマそのもので遊ぶとなると、スポーツカーやレース専用車などとなる。この場合、クルマはスポーツ・ギアの一種となるので、サーフボードやスキー板、テニス・ラケット、野球のグラブなどと同じことになる。
こうしたスポーツ・ギアも、その使い方で意味が変わってくる。勝敗が大切な競技では、これらは勝つための“道具”になるが、サーフボードにしてもスキー板にしても、競技で使うとは限らない。サーフボードであれば、ただ波にまかせて乗るのもよし、スキーであれば、ひたすら斜面を滑り降りるだけで楽しい。
クルマでいえば、レース専用車は速さを競う道具だが、スポーツカーはただ走るためのものだといってよい。ところで、ただ走るのが楽しいとは、というよりも、“楽しい”とはいったいどんなことなのだろうか。
■蝶も遊ぶ
カイヨワは、蝶が木の葉に似た色に羽を変色させる(擬態)ときに、枯れ葉や虫に食われた葉に上手に羽を似せるという。青々とした若葉に似せるよりも、ずっとリアル(自然)である。しかし、驚くことはない。人間も同じだ。蝶を模した舞台衣装もあるし、お祭りでは動物の仮面をかぶって踊る。ひたすら蝶や動物に似せようと必死になる。遊びでこうしたことをするのを、カイヨワは“模倣”というのだが、擬態を行う蝶も遊んでいるのだろうか。蝶も遊ぶとすれば、新鮮な発見だ。
子供のころ、電車ゴッコをした。道具はたった1本のひもだけである。輪を作って中に入る。先頭は運転手、中央はお客、後ろは車掌である。これで部屋の中や広場を走る。それだけのことだが、飽きずに毎日遊んでいた。たった1本のひもで電車を真似てしまうというのは、考えてみればすごい発想である。××ゴッコは、人間の擬態欲求の現れかもしれない。
■自然と遊び
子供に人気の遊びといえば、ブランコがある。これは、カイヨワのいうところの“めまい”感覚を楽しむものだ。サーフボード、スノーボードも、同じめまい感覚を楽しむ遊びといってもよい。インラインスケートやスケートボード、スノーボードのハーフパイプや、ジャンプしながら回転するスキーのエアーなど、いわゆるX系ゲームが人気だが、このめまい感覚は強烈だ。X系ゲームは、めまいを競争して楽しむ遊びかもしれない。人間に近い動物の猿は、枝を伝わって木から木へ飛ぶようにして渡る。猿もめまい感覚を楽しんでいるのだろうか。
室内ゲームも楽しいが、突然の雨や吹雪、風などの自然の変化が加わる野外ゲームは、さらに楽しい。これは、カイヨワのいう“偶然”の要素が、遊びの楽しさを倍加させる例だ。
森の中でかけっこをしたり、斜面を転がったりするだけでも楽しいが、考えてみると、自然の中で遊ぶと、カイヨワのいう遊びの4つの機能がそろっていて、楽しさに欠けることはないようである。
■ドライビング・プレジャー
19世紀末に自動車が誕生すると、人々はすぐに自動車で遊びはじめたのではないだろうか。しかし、ドライブを楽しむ前に、ラジエターに水を補給し、クランクを回してエンジンを始動し、暖気運転をしてと、大変な準備が必要だったにちがいない。
また、ドライブを楽しむといっても、クラッチをおそるおそるつなぎ、ままならないエンジンをだまし、入りづらいトランスミッションに悲鳴を上げて運転をした。これもドライブの楽しさだったにちがいないが、機械を調整したり、操作する楽しさが大きかったような気がする。
現代の自動車には、このわずらわしさはない。逆にいえば、こうした楽しみは味わえなくなった。
一方、家庭や職場を見まわすと、スイッチひとつで簡単に作動する電気製品に囲まれている。しかも最近は、その情報化がいちじるしい。機械を微妙に操作することから、電気のスイッチを入れ、情報を取り込んだり、発信したりすることへと、生活も仕事も大きく変化している。だが、自然との触れ合いはますます減っている。
■“私”が、ドライビング・プレジャーの元素
顕微鏡は、それまで知り得なかった生物の秘密をたくさん説き明かした。コンピューターは、人間の遺伝子のすべてを解き明かそうとしている。これらは、科学もまた、私たち人間も生き物であり、自然の一部だということを教えるようになったことにほかならない。
そして、自然がとても興味深いものであるのなら、その一部である私たちの“からだ”もまた、とても興味深いものにちがいないと気づきはじめたのだ。
カイヨワのいう遊びの4つの機能を自然が取りそろえているなら、人間のからだにもあるはずだ。自然との触れ合いが減っても、自分のからだと交信することでその一部は取りもどせるはずであり、“自分のからだと遊ぶ”というのは変な言い方だが、そもそも遊びとはそういうことだったのである。
次世代のドライビング・プレジャーは、クルマで遊ぶのではなく、クルマを介して自分のからだを遊ぶことになりそうだ。このとき、からだと外界の自然をインターラクティブに結ぶ情報技術が、重要な役目を果たすだろう。
(次号へ続く)

|
|
 |
 |
 |
 |
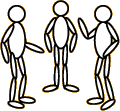
ここに(やや退屈気味の)仲よしの3人がいて……

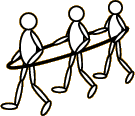
“電車ゴッコ”……楽しいかも?

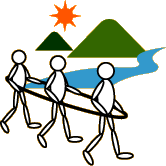
とはいえ、大のオトナが町中で……とは思ったので、大自然のなかで“電車でGo!”

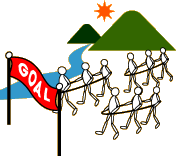
これに“競争”の要素を加え“全日本・電車ゴッコ・グランプリ”……という話ではありませんが……楽しいかも?!


こんな楽しさが味わえる、次世代型ドライビング・プレジャー……師匠の次回の講義で、その全容は明らかに! 待て、しばし!
|
 |
 |
 |
 |
|