 |
 |
 |
国際的取り組みの必要性 |
|
酸性雨は大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物が原因ですから、被害は国境を越えて起こります。そのため、国際間のネットワークや取り組みが必要になります。ヨーロッパでは、酸性雨に対するモニタリングが1970年代から開始され、国際間の調整が1980年代ごろから本格的にはじまりました。
ヨーロッパでの取り組み ◎長距離越境大気汚染条約 それまでに行われたモニタリングや報告により、ノルウェーが酸性雨に対する国際条約を結ぶことを提案し、1979年、国連欧州経済委員会(UNECE)において採択されたのがこの条約です。83年に発効し、1995年現在、40の国および機関が批准しています。各国に越境対汚染防止のための政策を求めるとともに、硫黄などの排出防止技術の開発、酸性雨影響の研究の推進、国際協力の実施、酸性雨モニタリングの実施、情報交換の推進、などが規定されています。 ◎ヘルシンキ議定書 長距離越境大気汚染条約に基づき、1987年に発効した硫黄酸化物に関する議定書です。署名した各国が、1980年時点の硫黄排出量の最低30%を1993年までに削減することを定めています。 ◎ソフィア議定書 こちらは窒素酸化物に関する議定書で、1991年に発効しました。1994年までに窒素酸化物の排出量を、1987年時点の排出量に凍結することを定めています。同時に、新規の施設と自動車に対しては、経済的に使用可能な最良の技術に基づく排出基準を適用しなければならないことを規定しています。また、無鉛ガソリンの十分な供給も義務づけています。西欧12か国では、1989年から10年間で窒素酸化物の排出量を30%削減することを宣言しています。 |
||
|
米国とカナダ間の取り組み ヨーロッパにくらべると遅れていた北米では、五大湖周辺の工業地帯で、米国とカナダ間の国際問題として酸性雨被害が顕在化しました。1980年には、米国で“酸性雨降下物法”が定められ、モニタリング、生態系の調査が実施されるようになりました。これが、10年をかける“全国酸性降下物調査計画”(NAPAP)でした。さらに、カナダは米国に対して硫黄酸化物の排出量を削減するように働きかけ、両国は条約締結のため調整委員会を設置することを合意、1991年には、酸性雨被害防止のため大気保全二国間協定を調印しました。1990年、NAPAPの終了後、米国は大気清浄法を改正し、硫黄酸化物や窒素酸化物の総量削減方策をそのなかに盛りこみました。 |
||
|
日本と東アジアでの取り組み 1983年から、環境庁では総合的な研究調査が開始し、これまで第一次(1983〜87)、第二次(1988〜92)、第三次(1993〜97)にわたり、降雨中のpHの測定と生態系に対する調査が行われました。この結果では、雨に含まれる酸性度は欧米なみではあるが、まだ生態系に対する影響は明らかには見られていないとされています。しかし、このまま、酸性度の高い雨が降りつづければ、これからの湖沼や森林への影響が心配されるとも指摘しています。 東アジア地域では、エネルギーを石炭に依存する国も多いことから、硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量が急激に増えています。当然これらからの被害も予測されるため、この地域でのモニタリングやネットワーク作りが重要と考えられます。そのため、環境庁では1993年以降、東アジア11か国および国際機関の担当者や研究者の参加をつのり、“東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想”を提唱しました。1997年には、ネットワークの設計が採択され、2000年までにネットワークの設置をすることを推進しています。 |
||
|
酸性雨の状況(pH年平均値) |
||
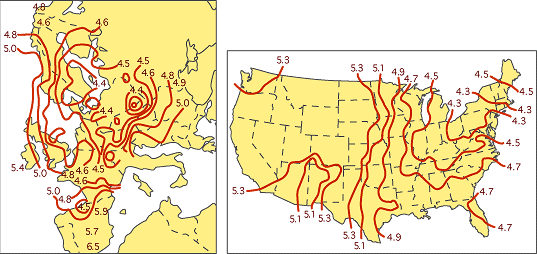
|
||
| [出典]『地球環境キーワード事典』 |
|
主要諸国の硫黄酸化物および窒素酸化物の排出量(1990年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
[出典]『地球環境キーワード事典』
[参考サイト] EICネット エコライフガイド 環境庁によるページ。酸性雨の解説など。 WNN-Ecology 酸性雨調査 WNNによる酸性雨の調査、結果。酸性雨クイズや質問コーナーもあります。 |
