 |
 |
 |
どこで、どのような被害が? |
|
死に絶える湖!
酸性雨にさらされると、まず川や湖沼に被害が現れます。水の酸性化によってプランクトンや水生生物が死滅し、魚もエサがなくなって死滅します。こうしてなにも生息できなくなった湖を、“死の湖”と呼びます。 ヨーロッパや北米では、多数の湖が“死の湖”と化してしまいました。スウェーデンでは21,500の湖が酸性雨の影響を受け、そのうち9,000の湖沼で魚類の生息に悪影響が出ています。ノルウェーでは、1,300平方キロメートルの地域で魚がいなくなり、カナダでは4,000の湖が死の湖と化し、米国では、アディロンダック山を中心に220の湖沼が酸性化しています。 |
||
|
枯れゆく森林! 次に訪れる被害は、森林被害です。毎年葉を落とす広葉樹よりも、葉をつけたままの針葉樹のほうが気孔にダメージを受けやすく、その被害が深刻になっています。 酸性雨は土のなかにも染みこみます。土のなかにあるマグネシウムやカルシウムが酸性雨の酸と化学反応を起こし流れ出してしまうと、樹木は栄養が不足して、成長が止まったり、病気や害虫にやられてしまいます。これが森林被害を助長し、樹木を枯らすのです。 酸性雨の被害はpHだけでなく、その他の大気汚染物質、その土地の気候、樹木帯、土壌の質などによって複合的にもたらされるのです。森林被害を受けたことで有名なのは、ドイツのシュバルツバルト(黒い森)など、ヨーロッパや北米に多いのも特徴です。また、中国でも重慶市近郊で、酸性汚染ガスによる健康被害や森林被害が起きています。 |
||
|
建造物が溶ける! 大理石、コンクリート、金属などで作られた建物、橋なども、酸性雨によって腐食します。とくに、大理石などで作られた歴史的建造物が酸性雨によって溶けていってしまうのは、世界的な損失です。アテネのパルテノン神殿や、ローマの遺跡、ドイツのケルン大聖堂など遺跡、石像などが被害にあっています。 |
||
|
日本ではどうなの? 1973年から76年にかけて、夏期に関東地方を中心に、霧雨や雨水によって人々が目や皮膚の痛みを訴えるという事件があったのをおぼえていますか? 小雨をともなう特殊な気象条件が生じた場合、雨のなかの酸性物質と、大気中の刺激物質が相互作用するものと考えられました。 その後、1983年から、環境庁が全国規模の調査が実施しています。調査結果によると、全国的にpHが“4”台の降雨が観測されつづけています。酸性度は欧米なみですが、生態系に対する明らかな影響は、まだ見られていません。 地域で見ると、人口や工場が集中し、山でさえぎられて空気が逃げない関東地方で、酸性度の高い雨が観測されつづけています。日本海側は、大陸からの季節風の吹く冬に、酸性度が高くなります。また、自動車の排気ガスによって、高速道路の周辺で高くなる傾向が見られます。 雨の酸性度を計ったり、被害を観測する作業は比較的容易で、朝顔の斑点(酸性雨にさらされると白い斑点が出る)で調べる調査などが、全国の学校ネットワークなどで調査されています。現在のところ日本では、生態系に明らかな影響は見られませんが、このまま酸性度の強い雨が降りつづくと、早い場合、約30年後に、湖沼の酸性化がはじまるとの予測もあります。 |
||
|
降水のpH分布(環境庁) |
||
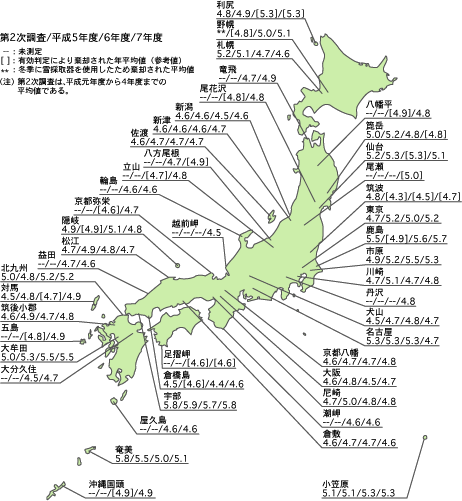
|
||
| [出典]『地球環境キーワード事典』 |
