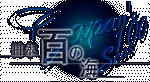
|
その16 玄海灘のシイラ漬漁 |
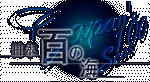
|
その16 玄海灘のシイラ漬漁 |

|
|
|
魚網という人間の“手のひら”に捕らわれた魚たち。 |
|
|
九州北西部の海、玄界灘は豊かな漁場として有名である。同時に、日本海の西の玄関口に位置するこの海は水深が浅く、岩礁が多いために荒海としても有名である。地元の漁師さんたちに聞くと玄界灘の豊かさが言葉の端々に感じられる。“いくら獲っても次々と魚がわいてくる海”として漁師さんたちの信頼厚い海、玄界灘はどうやって、そんなに豊かな生物を育んでいるのだろうか?
永い間の疑問に取り組むチャンスが今年の初夏に巡ってきた。福岡の放送局、RKB毎日放送と玄海灘の海洋生物に関するテレビ番組を作る事になったのだ。早速、玄海灘についての資料を調べると、背後に対馬海流と日本海の大きな影響が見えてきた。これは海洋学の専門家ではない私の素人考えではあるが、1つの推論として聞いてもらいたい。 日本海に流れ込む暖流、対馬海流は玄界灘を南西から北東に横切り日本海に入っていく。流れ込んだ対馬海流は日本沿岸に沿ってゆっくり走り能登半島、佐渡島を経て北海道西岸まで達する。対馬海流は北上するうちにゆっくりと冷やされ、水温を下げていく。以前は北海道まで達した海流はそのまま北上を続けると思われていたが、大陸と北海道の間の海底が非常に浅いため北上できず、反転して寒流のリマン海流となり、ロシア、中国の沿岸を南下し始めるというのが最近の調査から判ってきた。 簡単に言うと、日本海はお盆のように周囲が浅くなっているため南から来る対馬海流の流れ込みは北の狭い出口から排出されず、反転し再び南に戻るというわけである。しかも、北部の寒い天候に冷やされた海水は比重が重くなり、深い海底を南下し始める。南下するリマン海流は朝鮮半島にぶつかり方向を変え、玄界灘の浅瀬に湧昇流として湧き上がってくる。 湧昇流は深海にあるリン、カリウム等の栄養塩類を豊富に含んでいる。対馬海流が運んでくる植物性プランクトンがこうした栄養塩類を使って盛んに光合成して作り出す栄養分は、玄海灘の食物連鎖の原点を支え、豊かな水産資源を育んでいるというのが、にわか海洋学者の私が作り出した推論である。 玄海灘の豊かさの片鱗に触れたくてこの海ならではの漁、シイラ漬漁に行く若潮丸という漁船に同乗させてもらった。博多の北東約30キロにある鐘崎の漁港から出るシイラ漬漁は朝の3時出発、帰港時間は漁獲次第という厳しいものであった。シイラ漬漁といっても目的の魚はシイラではなく、ハマチ養殖用のブリの若魚を狙った漁であった。漁は、モウソウダケを10本近く束ね、目印を付けた浮きを沢山作り、固定するロープの端に土嚢の重りをつけて玄海灘の水深50〜70メートルほどの海底に沈め置き、ブイのように水面に浮くモウソウダケの周りに集まる小魚を一網打尽にする。外洋で拠り所を求めてホンダワラ等の流れ藻に群れ集まる魚たちの習性を利用した漁法である。 さて、港からはるばる6時間以上かけてたどり着いた漁場は、はるか彼方に対馬の島影が見える沖合いであった。船頭の八尋さんが珍しがるほどの凪の海に飛び込みシイラ漬漁を海中から見学することにした。まだ初々しさのある顔付きのブリの若魚が数百匹、網の中で右往左往しながら慌てふためいていた。混獲されたシイラは怒りに黄色く発色し、ブリの若魚たちは心なしか青ざめて見えた。 漁師たちは網の一箇所に魚を集めると魚体を傷つけないよう、慎重に掬い上げ生簀に運び入れる。  漁は80箇所以上も沈められているシイラ漬けを巡りながら延々と続けられた。大漁であった。人は朝日に学び、月夜に学ぶ。鳥に学び、クジラにも学ぶ。流れ藻から得た知恵は、人々に沢山の魚をもたらしたかもしれない。豊穣の海がその仕組みを失わない限り……。 漁は80箇所以上も沈められているシイラ漬けを巡りながら延々と続けられた。大漁であった。人は朝日に学び、月夜に学ぶ。鳥に学び、クジラにも学ぶ。流れ藻から得た知恵は、人々に沢山の魚をもたらしたかもしれない。豊穣の海がその仕組みを失わない限り……。
|
|
魚体を傷つけないよう、漁師たちは 慎重に魚たちを掬い採り、生簀に移す。 |
|
|